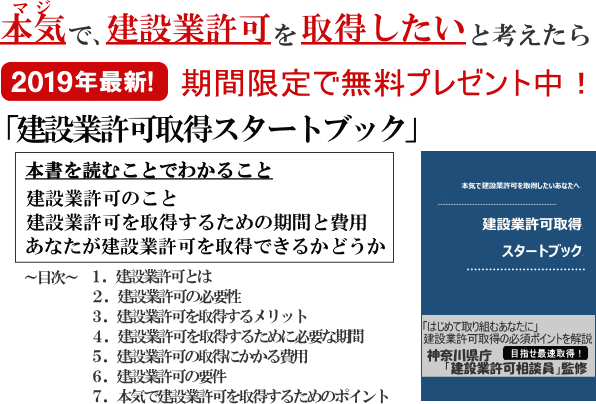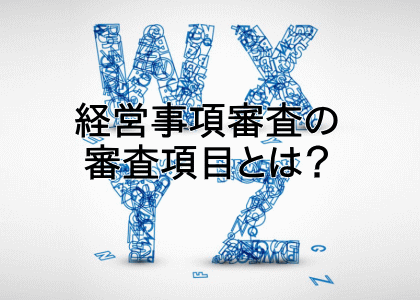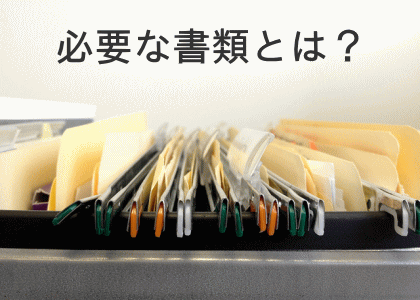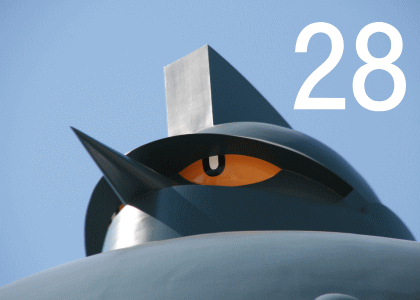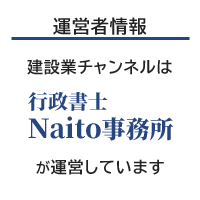入札参加資格の格付け(ランク)制度についてわかりやすく説明します。
入札参加資格の格付け(ランク)制度を理解するために4つのことをご紹介したいと思います。
- 入札参加資格の格付け(ランク)制度
- 客観的事項の評価
- 主観的事項の評価
- 格付け(ランク)の意味・必要性
入札参加資格の格付け(ランク)制度
入札参加資格の格付け(ランク)制度とは、格付け(ランク)による建設業者の棲み分けを行い、事業の規模・能力に応じた工事を受注させる制度のことです。
公共工事の発注機関は「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化し、格付け(ランク付け)を行います。格付け(ランク)は、段階評価となっており、そのランクに応じて受注できる工事金額が決まっています。
発注機関によってAからDの4段階評価や、AからCの3段階評価と、段階の数に違いはありますが、ランクが高いほど、受注できる公共工事の金額が高くなります。そのため、元請金額の高い公共工事を受注したいと考えるのであれば、高いランクを目指す必要があります。
ただし、気を付けていただきたいのが、ランクが高ければ高いほど良いというわけではない点です。入札参加資格の格付け(ランク)制度では、ランク毎に公共工事に入札出来る範囲が定められています。
下のランクの企業が上のランクの工事に参加することを禁止しているだけでなく、上のランクの企業が下のランクの工事に参加することも禁止されています。
つまり、高いランクを取ることにより、下位の工事を受注ができなくなる可能性があります。
そのため、格付け(ランク)は、とにかく高いランクを取れば良いというものではなく、どの規模の公共工事を受注したいかで目指すべきランクを検討しましょう。
客観的事項の評価
客観的事項の審査及び評価とは、公共工事の発注機関が経営事項審査の結果を基に評価を行うことです。
経営事項審査を受けると、「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価された結果通知が出ます。
この経営事項審査の結果通知書を用いて、客観的事項の審査が行われます。
主観的事項の評価
主観的事項とは、公共工事の発注機関が独自に評価する項目のことです。
発注者別評価と言われたりします。
「主観的」や「独自」という言葉が、発注機関の恣意性を連想させるかもしれませんが、基準を設置し、客観性・透明性をもって行われています。
発注機関ごとに、具体的な工事の性格、地域の実情、発注機関の目的などに基づいてそれぞれの判断で評価しています。
具体的には次のような項目があります。
- 地域内の過去の工事施工実績や表彰等
- 地域内の本店の有無
- 地域内の営業実績
- ISOの取得の有無
- 消防団協力事業所の認定
- 高齢者雇用事業所の登録
- 女性管理職雇用事業所の認定
- 建設業労働災害防止協会への加入状況
尚、主観的事項の審査・評価は必ずしも全ての発注機関で行われているわけではありません。体制の問題等から、特に市町村においては主観的事項の審査・評価は行われていないことも多いのが実情です。
また、主観的事項の審査・評価を行っていたとしても、主観的事項の内容や格付のランク表を公表していない発注機関もあります。そのため、入札参加資格審査の前に、各発注機関のホームページをチェックし、不明な点は発注機関の担当部署に確認しておきましょう。
格付け(ランク)の意味・必要性
なぜ、入札参加資格の格付け(ランク)を行っているかというと、建設業の健全な発展を促進するためです。
公共工事の競争入札は、原則的には価格競争です。価格競争は、大企業であればあるほど有利になります。
もし、格付け(ランク)を設けずに、入札に全ての建設会社が参加できるとしたらどうなるでしょうか?
大企業は建設資材や材料を大量に安く購入することが出来るため、結果として安価で入札が出来ます。そうなると、中小企業の建設業者は入札をしたとしても価格で負けて、落札できなくなります。
もし、中小企業が価格競争で勝つためには、人件費を削るしかありません。
中小企業が落札するために、人件費を削ってでも安値で入札を行うことは、果たして建設業の健全な発展につながるでしょうか?
中小企業の建設業者が成長・発展しなければ建設業の発展もありえません。
そのため、入札参加資格に格付け(ランク)を行い、小規模工事にまで大企業が進出してこないようにしているのです。
中小企業の建設業者を保護し、健全な競争が行われ、建設業全体が成長・発展するために格付け(ランク)が行われているのです。